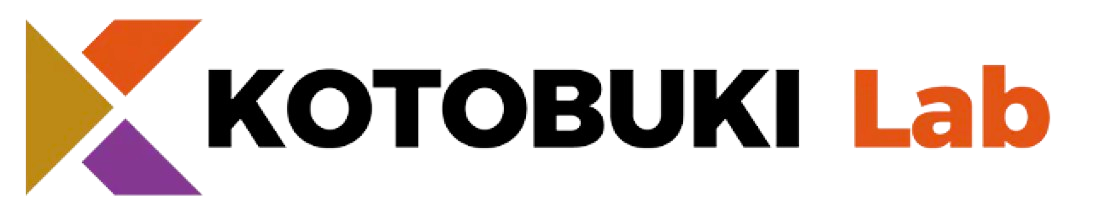私の自宅の最寄り駅には大きな書店があり、時間がある時に本を物色するのが日課です。
今狙っているのは「地球の歩き方 ムーJAPAN ~神秘の国の歩き方~」
です。
ジャンルで言うと趣味にカテゴライズされると思うのですが、興味本位で購入するには、なかなか良いお値段ではありますので、若干悩み中ですが近く購入していることでしょう。。
↑とは別で、行動経済学に関する書籍を読みました。
こちらはマーケティング的に何か学びがあればと思い手に取りました。
行動経済学は、伝統的な経済学の枠組みを超えて、人間の心理的・感情的な要因が経済的意思決定にどのように影響を与えるかを研究する学問です。従来の経済学は、人間が合理的かつ自己利益を最大化するように行動することを前提としていますが、行動経済学は、人間がしばしば非合理的な行動を取ることを前提としています。
人間のサガ、本能に近いのかもしれません。
行動経済学の主要な概念と理論をいくつか紹介します。
プロスペクト理論
この理論は、人々がリスクに対してどのように意思決定を行うかを説明しています。主な特徴として、以下の点が挙げられます。
参照点依存性
人々は絶対的な結果ではなく、ある基準点(参照点)に対する相対的な変化として利益や損失を評価します。
損失回避
人々は同じ金額の利益よりも損失の方をより強く感じます。例えば、100ドルの損失は100ドルの利益よりも痛みを伴います。
非対称な価値関数
利益と損失の評価は非対称であり、損失の方が利益よりも急勾配で評価されます。
アンカリング効果
アンカリング効果とは、人々が最初に与えられた情報(アンカー)に基づいて意思決定を行う傾向があることを指します。例えば、商品の価格を評価するときに、初めに提示された価格がその後の判断に大きな影響を与えます。この効果は、購買行動や価格交渉において重要な役割を果たします。
確証バイアス
確証バイアスは、人々が自分の信念や仮説を支持する情報を優先的に求め、反対する情報を無視する傾向を指します。これにより、誤った信念や偏見が強化されることがあります。確証バイアスは、投資やビジネス戦略の策定において重要な影響を及ぼします。
フレーミング効果
フレーミング効果は、同じ情報でも提示の仕方によって人々の意思決定が変わることを指します。例えば、ある病気の治療法が「成功率90%」と提示される場合と「失敗率10%」と提示される場合では、同じ内容であっても受け取られ方が異なります。この効果は、マーケティングやコミュニケーション戦略において重要です。
社会的影響
行動経済学では、個人の意思決定が他者の行動や社会的規範によって影響を受けることも研究されています。例えば、ソーシャルプルーフ(社会的証明)やノーミング(社会的規範)の効果があります。これらは、個人が他者の行動を参考にして自分の行動を決定することを説明します。
行動経済学は、経済的意思決定における人間の心理的要因を理解するためにとても有効な方法論だと思います。これらはビジネス戦略の策定だけでなく、普段の生活において人間関係をスムーズにしたり、気分をコントロールしたりと色々なことに役立てることができそうな気がします。
弊社はオフショアシステム開発やセキュリティ診断、DX支援などを行う会社ですので、これらの行動経済学を学び自社やお客様の発展に役立てることができるかもしれないなと考えております。
皆さんも興味を持っていただければぜひ行動経済学の書籍を手に取ってみてください!